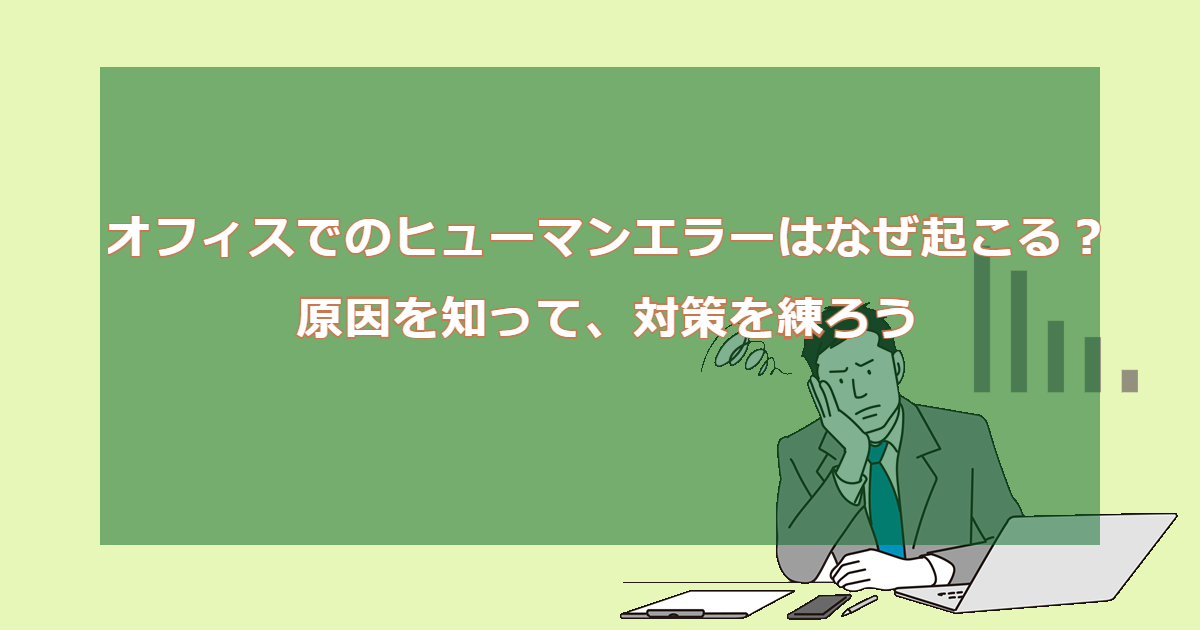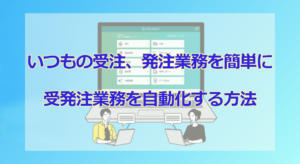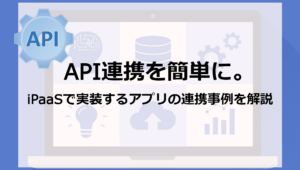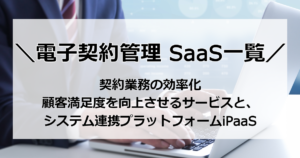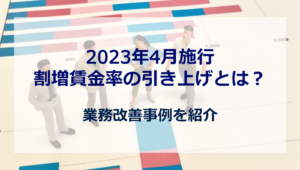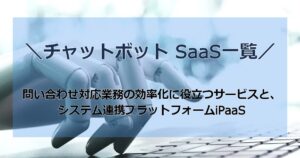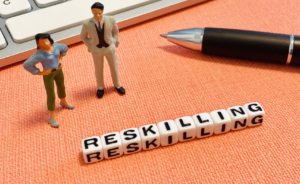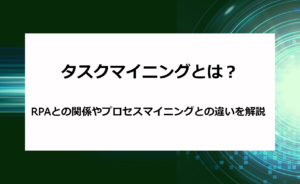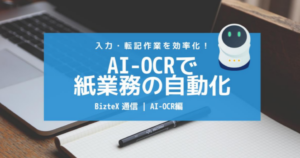ヒューマンエラーとは
ヒューマンエラーは、人間が行う活動や判断の過程で起こる誤りやミスのことを指します。人間が情報の処理や意思決定をおこなう際には、さまざまな要因が関与するため、時には誤った判断や行動をとることがあります。
ヒューマンエラーは、以下のような要因によって引き起こされることがあります。
ヒューマンエラーはなぜ起きるのか?4つの原因とは
社内での連絡、伝達漏れから大切なクライアントとの関係を損失してしまうような大きなものまで、ヒューマンエラーはあらゆるシーンに潜在しています。
ヒューマンエラーは誰もが起こすものです。だからこそ、人為ミスを発生させない工夫やリスクを最小限にするための対策が大切になります。
本記事では、なぜヒューマンエラーが起きるのかを大別してご紹介します。あらゆるシーンにおける注意喚起項目として確認しましょう。
先入観や思い込みによる勘違い
「そうだと思っていた」など、担当者が先入観や固定観念にとらわれてしまい、無意識に決めつけることで、ヒューマンエラーが発生することがあります。
端的言えば勘違いによるミスです。例えば、タスクの納期を間違って覚えていた、使い込んでいた表計算ソフトの関数が間違っているとは思わなかったなどが挙げられます。
文字通りに「思い込みによるミス」なので、ここは常にマニュアルや正しい工程にそって作業する習慣づけ、さらに言えばそういったルール作りが必要となります。
思わぬ見落とし
「昼食後に社内に戻ると実は午後一の社内ミーティングを忘れていた」といったケースはありませんか?
このように予定表やルール、フローなどの見落としもヒューマンエラーの代表的なもの。
例えば、大切なクライアントからのメールを見逃していた、などものこのケースです。
慣れや自己流によるやり忘れ
業務を任せきっていた信頼するベテランスタッフ、あるいは長い付き合いのクライアントなどで生じるケースが多いヒューマンエラーの原因が「慣れや自己流によるやり忘れ」。いわゆる属人化です。
例えば自社スタッフの慣れが原因のものを例にあげれば「毎月のことなので、上司への報告時に、顧客からの伝達事項を追記、伝言することを忘れた」。あるいは逆に「部下から頼まれた書類の承認業務を忘れた」などです。
逆にクライアントなど相手との関係が親しいがあまりに生じるミス、ヒューマンエラーとしても同様に伝達ミスや失念などが起こりえますが、最も避けたいのは関係が深いがために、上司の判断などを仰がず、自己判断で進めてしまうことです。この場合、ヒューマンエラーに加えてブラックボックス化しており、大きな問題に発展しやすいので注意しましょう。
ヒューマンエラーの防止策としても有効なのですが、各工程は肩書や部署に関係なく、なるべく広く、見える化させておくことがエラーの早期発見や問題を大きくしないために重要です。
認知力、注意力の低下
新しい部署への転属や入社間もないなどの環境の変化、長期の拘束、疲労など置かれている状況によって認知力や注意力が低下しているときは、ヒューマンエラーが起きやすくなります。
例えば、業務中に電話が入り、雑な作業になってしまったり、残業中など睡魔によって集中力が途切れた際のミスです。
こういったミスを防ぐためには、やはり環境の変化やミスをしやすい状況があり、そういったケースでは「自分はミスをしている可能性がある」と意識し、見直すことが必要です。
ヒューマンエラーを起こしやすい人はどういう人?
ビジネス現場におけるヒューマンエラーを起こしやすい人には、以下のような傾向があります。もちろん、個人の能力や状況によって異なるため絶対的ではありません。
ストレスへの対処能力が低い
ビジネス現場ではしばしばストレスが発生します。ストレスが高まると、判断力や注意力が低下し、ミスを引き起こしやすくなる傾向があります。
注意力や集中力に欠ける
細かい作業や手順の確認が必要な仕事では、十分な注意力や集中力が求められます。注意散漫な人は、ミスを起こしやすくなる可能性があります。
マルチタスキングが苦手
多くの業務やプロジェクトを同時に管理する必要がある場合、マルチタスキング能力が求められます。マルチタスキングが得意でない人は、業務の遂行や優先順位の管理においてエラーを起こしやすくなるかもしれません。
経験不足や知識不足がある
特定の業務やタスクに関する経験や知識が不足している場合、ミスを引き起こすリスクが高まります。適切なトレーニングや教育の提供が必要です。
自己管理能力が低い
デッドラインや優先順位の管理、タスクの計画など、自己管理能力が求められる業務では、自己管理が苦手な人はエラーを起こしやすくなる可能性があります。
ヒューマンエラーを防止する効果的な5つの考え方

ヒューマンエラーが発生しやすい原因についてご紹介しました。では、どのようにすればそれらを防止できるでしょうか。
具体的な施策をお伝えする前に、まずはそれらを防止するために必要な考え方を見ていきましょう。ざっくりいうと、次の5つがエラーを防止するために必要な考え方です。
- エラーを誘発する業務自体をなくしてしまう
- エラーをおこさせない
- 業務をわかりやすくする
- 知覚させる
- 予測させる
一つずつ見ていきましょう。
エラーを誘発する業務をなくしてしまう「機会最小」
逆説的にはなりますが、ヒューマンエラーを防ぐために最も効果的な対策は、エラーを誘発する業務そのものをやめることです。
エラーというものは実施する必要がある業務にともなって起こるものです。つまり、そもそもリスクのある業務を無くすことができれば、エラーも無くなるという考え方です。この考え方を機会最小といいます。
機会最小とは文字どおり、エラーにつながる機会を最小化するものです。ヒューマンエラーの対策では、基本的に機会最小から検討すべきです。リスクのある業務を「やめる」「なくす」「減らす」という対策は、あらゆる対策の中でも極めて効果が高いからです。
ただし、業務をすべてやめることは難しいことではありますが、業務の中でムダな行為を無くしたり、無理のある状況を改善したりすることは有効でしょう。また、リスクがともなう業務を可能な限り減らすというのも大切になります。
エラーをおこさせない「フールプルーフ」
ヒューマンエラーを防止するために、エラーをできなくするという考え方がフールプルーフです。これは、実際に業務をやめるのではなくエラーを起こすことができないようにすること。
例えば、自動車がブレーキを踏みながらでなければエンジンを始動できなかったり、蓋を閉めないと洗濯機のドラムが回転しないのは、この例にあたります。
このように、設計や計画の段階で起こりうるエラーを洗い出し、それが物理的に生じない工夫をあらかじめ実施することが大切です。
業務をわかりやすくする/やりやすくする
ヒューマンエラーは複雑な状況や人間の認知能力を超えるような場面で誘発しやすくなってきます。そのため、可能な限り業務をわかりやすくすることが重要です。
エラーを誘発する可能性がある状況を、わかりやすくすることによって簡単なミスやエラーを回避できます。わかりにくい状況は認識や判断を誤らせ、エラーを起こしやすくなるという考え方です。
業務をわかりやすくするために有効な手段は整理整頓、そしてマニュアルの作成です。ちなみに掃除などを伴う整理整頓はもちろん、業務の整理整頓も含みます。
知覚させる/気づかせる
ヒューマンエラーの防止を狙い、公道の急角度のカーブ地帯には危険を知らせる標識があったり、宅配品などには「割れ物」と書かれたシールが貼られてあったりと、注意を促す工夫がなされていることがあります。
これらは、「人間はまれに危険な状況を見落とす」ことを考慮したもの。できる限り早い段階で危険を知覚させ、注意を促しています。
このようにミスを知覚させる、気づかせる有効な手段のひとつがダブルチェックです。ただし、ダブルチェックについて注意したいのは、ただ単純に複数回の確認作業をおこなうのではなく、万全の状態で念の為に確認してもらうということの意識付けです。ダブルチェック前提のダブルチェックでは効果が望めないので注意しましょう。
予測させる/能力をもたせる
あらかじめ危険予知トレーニングをおこなって、リスクに対するリテラシーを高めることも重要な対策です。リスクは想定していないと回避することができません。そのため、日頃からリスクを予測する習慣を身につけることが大切です。日常の中にある些細な危険にも目を光らせ、気づいたらすぐに改善するという癖をつけましょう。
「能力をもたせる」とは、技術的なスキルアップだけでなく、リスクに対するリテラシーを向上させることをいいます。組織において教育体制を整備したり、定期的に研修などを行うことが有効です。
また、基準を設けて、能力があると判断できる者にのみ業務をおこなわせるという対策が必要な場合も。能力をもたせるには、組織的な教育体制の確立と学習する文化の醸成が必要になるでしょう。
ヒューマンエラー対策!有効な3つの方法
ヒューマンエラーは起こるもの。それであれば、どれだけのその数を減らせるか、そして問題を大きくしないかです。そこで有効な方法な何か。即効性のある3つの方法をご紹介します。
マニュアル作成「誰でもできる化」
ヒューマンエラーは複雑な状況や人間の認知能力を超えるような場面で誘発しやすいとご説明しました。これを解消する最も有効な方法がマニュアルの作成です。
マニュアル作成時の重要ポイントはふたつ。ひとつが多くの人にチェック&レビューしてもらうこと。そしてふたつめがさらに常に内容をアップデートすることです。
いずれも、いつ、誰が見てもマニュアルとして参考になるという目的があります。
くれぐれもマニュアルを読み解くためのマニュアルが必要であったり、マニュアルの内容そのものが属人化していないよう気をつけましょう。
グループウェアの活用「各人のタスクの見える化」
ミスに周りがなるべく早く気づけること、フォローしやすい体制を作るために有効なのがグループウェアの活用です。
今、誰が何をしているのかを見える化することで将来、発生しうるヒューマンエラーの芽を刈り取る、深刻化するまえに沈静化する効果が期待できます。
グループウエアの活用の際に考慮すべきは、入力方法と項目の共通化です。ある担当者は昼食時間、どこに行くかまでも記載しているが、ある担当者は終日「作業」とだけ書かれていては効果を発揮しません。
▼業務体制の見直しに活用できる業務自動化診断レポートを無料で提供しています。
\自社の自動化できる業務がわかる/
定型業務の自動化「RPAの活用」
ヒューマンエラーを誘発する業務をなくすのに効果的な手法が定型業務の自動化です。
疲れや慣れからくるミスの誘発要因がないロボットに単純作業を任せることは、同時に工数の削減や、業務効率化などにも繋がります。
また、ロボットの費用は人件コストよりも安価な場合が多いです。人手不足が課題となる企業は、RPAの導入を検討してみるのもおすすめです。
▼RPAについては下記資料でわかりやすく簡単に解説しています。ぜひダウンロードしてご確認ください。
\事例を含めて5分でRPAがわかる/
【お問い合せ】思い込みや勘違いから発生するヒューマンエラー。RPAで解決しませんか?
ヒューマンエラーは、思い込みや勘違い、見落とし、慣れによってどうしても発生してしまうものです。ヒューマンエラーは、誰にでも、どの現場、どのタイミングでも生じるもの。それであれば、ヒューマンエラーをあるものとして許容し、いかにこれを防ぐのかを考えていくことが建設的でしょう。
とはいえ、それでも企業に甚大な被害を及ぼしかねないヒューマンエラーは、できるだけ最小限におさえたいところです。
例えばヒューマンエラーが発生しやすいケースのひとつ、事務処理業務など毎日発生する定型業務は自動化してくれるRPAに任せる――といった業務改善をするのも一つの方法です。RPAの導入により、生産性が向上する事例は多くあります。下記で業界別の活用例をご紹介しておりますので、ぜひご確認ください。
RPAとはどのようなものなのか、どのような業務を自動化できるのか、ご興味があればぜひお気軽にBizteXまでお問合せください。
RPAや業務効率化、業務の自動化、業務改善に関すること、その他クラウドサービス(iPaaSやAI-OCR、受発注システム)のことなど、御社のお悩みをお聞かせください。
業務体制の見直しに活用できる「業務自動化診断レポート」を体験しませんか?【無料提供中】
BizteXでは、 組織内のどの部門の業務を自動化できるのか。使っているシステムと同士を連携し業務自動化を図ることで、どのような効果がえられるのかなど業務効率向上を図るための「業務自動化診断レポート」を無料で提供しております。
方法はカンタンで、10問程度のアンケートにお答えいただくだけ。社内業務の体制見直し時にもご活用いただける診断レポートを提出いたします。
こちらの診断に費用は一切かかりませんので、お気軽にご利用ください。
\自社の自動化できる業務がわかる/